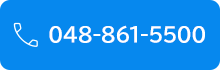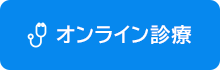腰椎椎間板ヘルニアとは

腰椎椎間板ヘルニアとは、腰の背骨と背骨の間にありクッションとしての役割をもつ「椎間板」に亀裂が入り、背骨の間から外へ飛び出してしまう疾患です。
飛び出だした椎間板によってそばを通る神経が圧迫されると、強い腰痛や足の痛みが起こります。突然腰やお尻に痛みが現れ、時間が経つにつれて脚の痛みやしびれが起こったり痛みが強くなったりする特徴があります。
そのほか、動けないほど痛みが強かったり、痛みによって眠れないなどの症状が起こることも多いです。
また、腰椎椎間板ヘルニアは前かがみの姿勢や重いものを持ち上げようとすることで症状が悪化することがあります。20~40代の方に多く見られ、男性の方が発症しやすいとされています。
高齢者の場合は、腰部脊柱管狭窄症を併発している場合があります。
腰椎椎間板ヘルニアの発症部位
腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎の5つの椎体(積み木上に重なる背骨)のうち、第4腰椎(上から4番目の椎体)と第5腰椎(上から5番目の椎体)の間の椎間板と第5腰椎と仙骨の間の椎間板に発症することが多いです。
高齢者の場合は第1腰椎から第4腰椎の間の各椎間板にヘルニアが生じることもあります。
腰椎椎間板ヘルニアの症状
腰椎椎間板ヘルニアの症状は、腰やお尻の痛みやしびれから始まります。
症状が進行すると、どちらか片側の下肢にも痛みやしびれなどの症状が現れるようになり、動けないほど激しい痛みが2~3週間程続きます。
特にお尻から太ももの裏にかけて痛みが現れる「坐骨神経痛」はヘルニアの特徴的な症状です。
歩行障害や痛みをかばうために身体を横に曲げることによる脊椎の変形が起こることもあります。
歩行障害は高齢者の腰椎椎間板ヘルニアの患者に多く見られます。症状がさらに進行し、膀胱に神経障害が起こると、排尿・排便障害が起こります。症状はせきやくしゃみによって悪化することがあります。
セルフチェック
下記の症状が当てはまる場合は、腰椎椎間板ヘルニアが疑われるため、整形外科を受診し検査を受けましょう。
- 突然、腰や足に痛みが起こった
- 痛みやしびれがある腰・足に体重をかけると、症状がひどくなった
- 安静時でも、痛みやしびれが治らない
- 階段を昇る時、足が持ち上がりにくくなる
下記のような筋力低下や排尿・排便障害がある場合は、腰椎椎間板ヘルニアが進行していると考えられるため、すみやかに整形外科を受診してください。
- つま先歩きができなくなった
- かかと歩きができなくなった
- 座った姿勢で、足の親指を上にあげることができない
- 肛門周囲が痺れている、感覚がなくなった
- 尿意を感じにくくなった、尿が出にくくなった
- 失禁(尿・便が漏れる、漏れる感覚が分からない)
腰椎椎間板ヘルニアの原因
腰椎椎間板ヘルニアの原因は、主に加齢や腰への負荷の高い職業、ライフスタイル、遺伝などによって、椎間板を構成する髄核が後方へ飛び出て、脊髄や神経根が圧迫されることです。
加齢
加齢とともに、椎間板の弾力性が失われることで、椎間板に亀裂が入りやすくなり、ヘルニアを発症しやすくなります。
仕事(製造業に従事している方・ドライバーの方など)
長時間の起立や着座を必要とする仕事や、重いものを持ち上げる、腰をかがめる動作が多い仕事は、腰椎に負担をかけるため、ヘルニアを発症しやすくなります。
タバコ
ニコチンは血管を収縮させる作用があるため、喫煙によって椎間板周辺にある血管が収縮することで、椎間板周囲の毛細血管へ栄養が届かなくなり、椎間板が変性しやすくなります。
遺伝子(遺伝)
10代で発症するヘルニアは、遺伝による影響が強いと考えられています。
椎間板には血管が通っていないため、一度椎間板を損傷すると、自然治癒によって回復することは望めません。
腰椎椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴
- 肥満体型である
- 猫背など、姿勢が悪い
- 普段から、仕事や育児などで、よく中腰・前かがみの姿勢をとる
- よくハイヒールを履いている
- 重い物を持つ、腰を強くひねる動きをよく行う
- 長時間座り続ける、または立ち続ける仕事に就いている(運転手・接客業など)
腰椎椎間板ヘルニアの
検査・診断
腰椎椎間板ヘルニアの検査では、触診や画像検査を行い、椎間板ヘルニアを引き起こしている根本原因を特定します。
検査の結果に基づいて、適切な治療を行っていきます。
問診・視診・触診
問診では、症状や症状が始まった時期についてお伺いします。
椎間板ヘルニアは咳やくしゃみが原因で起こることがあります。
触診では、筋力や感覚、腱反射などの検査を通じて、どの椎骨の間の椎間板が飛び出ているかを調べます。
特に第4腰椎と第5腰椎の間の椎間板がヘルニアを起こしている場合は、足の親指を上に挙げると筋力が弱くなるといった特徴があります。
下肢伸展挙上試験
(かししんてんきょじょうしけん:SLRテスト)
下肢伸展拳上試験(SLRテスト)とは、腰椎椎間板ヘルニアが疑われる場合に行われるテストで、脚をピンと伸ばしたまま、脚を持ち上げた際に、太ももの裏やふくらはぎ、すねの外側に痛みが生じるかを調べます。
また、腰椎椎間板ヘルニアのテストとして、大腿神経伸展テスト(FNSテスト)を行うこともあります。大腿神経伸展テスト(FNSテスト)とは、第1腰椎と第2腰椎の間や、第2腰椎と第3腰椎の間、第3腰椎と第4腰椎の間の椎間板にヘルニアが生じていることが疑われる場合に行われるテストで、うつ伏せの状態で腰を抑えて、膝を持ち上げた際に、太ももの表やすねの内側に痛みが生じるかを調べます。
しかし、高齢者の場合は、腰椎椎間板ヘルニアであっても、どちらのテストも痛みが起こらない傾向があります。
MRI検査
MRI検査は、椎間板を詳細に画像として確認できるため、椎間板のヘルニアの確定診断を行うことができます。
ただしMRI検査によって腰椎椎間板ヘルニアが生じていることが確認できても、症状がない場合は、積極的に治療を行う必要はありません。
なお、MRI検査が必要な場合、提携先の医療機関を紹介いたします。
X線検査
(レントゲン検査)
椎間板は軟骨組織であるためX線(レントゲン)検査では写し出すことができませんが、椎間板ヘルニアに似た症状が猫背や反り腰、腫瘍、脊柱変形などによって起こることがあるため、これらが起こっていないかを確認するためにX線検査を行います。
またX線検査の結果に応じて、CT検査や神経検査、椎間板造影検査、神経根造影検査などを行うことがあります。
腰椎椎間板ヘルニアの治療法
腰椎椎間板ヘルニアは、手術によって治療することがほとんどでしたが、近年の研究によって腰椎椎間板ヘルニアは発症から2~3ヶ月程度で自然に症状が軽減することが多いことがわかってきました。
そのため当院は腰椎椎間板ヘルニアの治療では、すぐに手術を行うのではなく、なるべく保存療法(薬物療法・装具療法・物理療法・運動療法など)を優先的に行います。そして、保存療法によって症状の改善がみられない場合や、歩行障害や排尿・排便障害が現れている場合に手術を検討します。
腰椎椎間板ヘルニアの保存療法では、薬物療法や物理療法で痛みを軽減するだけでなく、コルセットを用いる装具療法や運動療法を併用して腰への負担を減らし、症状の改善を目指します。
保存療法
保存療法では、以下のものを状態に合わせて選択します。
局所安静
痛みが強い時期は、安静にして痛みが軽くなるのを待ちましょう。
逆に痛みが落ち着いてきたら、体を積極的に動かし、筋力や可動域を低下させないことが重要になります。
痛い時は以下の安静姿勢で
過ごしましょう
痛みがあるときは、膝と股関節を少し曲げた姿勢や、丸めた布団などを敷いて上半身を少し持ち上げた姿勢、膝下にクッションなどを敷いて膝を曲げた姿勢を取ることが推奨されています。
薬物療法
薬物療法では、消炎鎮痛剤や筋弛緩薬などを用いて痛みや炎症を和らげます。
痛みが強い場合はブロック注射を行い、できるだけ痛みが強い時期をやり過ごします。
当院では、仙骨から下部腰椎の硬膜外腔に麻酔薬や抗炎症薬、ステロイド薬を注入する「仙骨硬膜外ブロック注射」や超音波(エコー)画像で患部を確認しながら、筋膜や神経、血管の周囲の組織に薬液を注射することで癒着を剥がす「ハイドロリリース注射」に対応しています。
痛みが強い時期が過ぎたら、運動療法を開始します。
物理療法
物理療法では、温熱、超音波、低周波、電気などを用いることで、血行を改善し、痛みを緩和したり、筋肉や関節の可動域を改善します。
運動療法
運動療法では、リハビリテーションを中心として、姿勢や動き・可動域の改善や筋力を向上させることで腰への負担を軽減し、症状の悪化や再発を防ぎます。
運動療法は、痛みが落ち着いてきた時期に開始します。
装具療法
装具療法では、コルセットや腰椎バンドと呼ばれる装具を用いて、腰を固定し、腰椎を安定化させることで腰への負担を軽減します。
装具療法は痛みが強い急性期に行う治療法であり、装具の長期使用は筋力低下を招き、ヘルニアの再発リスクを高めるため、装具を継続して着用できる期間は2~3ヶ月程度です。
痛みが強い時期が過ぎたら、装具を着用したまま運動療法を開始していきます。
手術
(MED法・PELD法・MD法)
腰椎椎間板ヘルニアの手術では、内視鏡を用いて飛び出した椎間板を摘出する「内視鏡下椎間板摘出術(MED法/PELD法)」や、顕微鏡視野下で内視鏡を用いて飛び出した椎間板を摘出する「顕微鏡下椎間板摘出術(MD法)」などがあります。
手術が必要となる場合は、提携する医療機関をご紹介いたします。
腰椎椎間板ヘルニアの予防
腰椎椎間板ヘルニアを予防するためには、
以下が効果的です。
「正しい姿勢」を心がける
腰に負担がかかるような姿勢や長時間同じ姿勢を維持することを避けましょう。
特にうつ伏せ姿勢は腰への負担が大きいため、改善しましょう。
また、マットレスや敷布団は、硬めのものを選ぶことで腰への負担を軽減することができます。
肥満の方はダイエットを行う
肥満は腰への負担を大きくするため、肥満の方は適度な運動によって減量しましょう。
中腰での作業は控える
重たいものを持ち上げるときは、中腰姿勢は避け、なるべく膝を曲げて脚を使って持ち上げるようにすることで、腰への負担を減らすことができます。
また、高いところにあるものを取る際には、踏み台などを使用して、なるべく腰を反らさないようにしましょう。
負荷に耐えられる
身体作りを行う
腹筋や背筋を鍛えることで、腰痛を予防することができます。
腹筋は特に体幹を安定させる上で重要です。腹筋や背筋のストレッチも、痛みの軽減に効果的です。