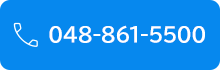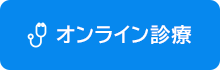再生医療とは
 再生医療は、外傷や疾患などによって失われてしまった体の機能を、人の体にある「再生する力」を用いて、もとに戻す治療法のことです。
再生医療は、外傷や疾患などによって失われてしまった体の機能を、人の体にある「再生する力」を用いて、もとに戻す治療法のことです。
当院では、今まで手術によってしか治療ができなかった障害や、後遺症に対して再生医療を行うことで、日常生活やスポーツへの早期復帰を目指します。
このような方に
PRP療法・幹細胞治療はお勧めです!
スポーツ選手や長期間のリハビリテーションで効果が得られなかった方にお勧めです。
アメリカではプロのアスリートが利用することが多い治療法で、野球の田中将大選手や大谷翔平選手が受けたことがある治療法として知られています。
- スポーツで関節や筋・腱・靭帯を痛めた方
- 変形性膝関節症と診断され、お悩みの方
- 階段の昇り降り時、関節に負担を感じている方
- 関節炎と診断後、様々な治療を試しているが改善が見られない方
- 手術を避けたいと考えている方
- 関節に違和感があり、同じ治療法を続けても効果が実感できない方
PRP療法について
 PRP療法は、患者様の血液から血小板を抽出し、PRP(多血小板血漿)を作り、それを体の損傷部位に注入することで、炎症や痛みを改善する治療法です。
PRP療法は、患者様の血液から血小板を抽出し、PRP(多血小板血漿)を作り、それを体の損傷部位に注入することで、炎症や痛みを改善する治療法です。
PRPは、組織の修復を促進する因子を多く含んでいます。PRP療法は、難治疾患や完治するまでに時間がかかる怪我などの治療に用いられ、整形外科だけでなく、歯科や形成外科など、様々な診療科で用いられています。
整形外科におけるPRP療法は、主に関節炎やスポーツ障害・外傷、変形性膝関節症の治療に対して行われます。変形性膝関節症の治療では、従来ではヒアルロン酸注射や運動器リハビリテーションで治療効果が現れない場合、次の選択肢は手術となる場合がほとんどでした。
しかし、再生医療の登場によって、手術をする前の選択肢を増やすことができるようになりました。
PRP療法の適応疾患
- 変形性関節症
(中年~高齢者が発症しやすい肩・肘・股・膝の痛み) - テニス肘(上腕骨外上顆炎)
- ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)
- 野球肘
- 膝半月板損傷
- 肩腱板損傷
- 捻挫・靭帯損傷
(膝内側側副靭帯損傷、前距腓靭帯損傷など) - アキレス腱炎
- ジャンパー膝(膝蓋腱炎)
- 肉離れ
筋・腱・靭帯損傷
筋・腱・靭帯損傷は、筋肉や腱、靭帯に過剰な負荷がかかることで発生します。
腱や靭帯は筋肉に比べると血流が少なく、治りにくいため痛みが慢性化することも少なくありません。
急性期のみならず、慢性化した疼痛に対してもPRPは一定の効果が得られています。
慢性疼痛
慢性疼痛とは 慢性疼痛とは、治療後も3ヶ月以上にわたって痛みが続く状態です。
国際疼痛学会では、「治療に要すると期待される時間の枠を超えて持続する痛み、あるいは、進行性の非がん性疼痛に基づく痛み」と定義しています。
痛みが慢性化していると、睡眠や仕事など日常の様々な場面に支障をきたし、意欲が低下する原因にもなります。
国内の患者数は、全人口の22.9%となっており、4人に1人程度は慢性疼痛に悩んでいる状況です。
年齢別では30代から60代までが最も多く 、様々な年代で起こるリスクがあります。
急性痛は、身体の異常を知らせるサインであり、多くの場合、その原因を特定して効果的な治療を行えます。
一方で、慢性疼痛は痛みの原因がはっきりしない場合があり、診断や治療が難しいことがあります。この理由は、神経の可塑的な変化や神経炎症などの器質的要因と、心理的・社会的要因が複雑に絡み合っているためです。
変形性膝関節症に対する
PRP療法での治療
PRP療法は、変形性膝関節症の治療に対して一定の効果があり、よく用いられている治療法の1つです。
変形性膝関節症に対する治療では、「PRP療法」と後述する「幹細胞治療」の2種類の再生医療を併用して行うこともあります。
PRP療法での
変形性膝関節症治療の効果
PRP療法は、変形性膝関節症の軟骨のすり減りや半月板の損傷、膝に水が溜まるといった症状に対して組織の修復を促し、関節の炎症を抑える効果があります。
従来の変形性膝関節症の治療は、薬物療法やヒアルロン酸注射が主でしたが、これらの治療の効果が感じられない場合は、PRP療法によって症状が改善する可能性があります。
PRP療法での
変形性膝関節症治療の経過
PRPを患部に注射すると、注入した部位の細胞が増殖し、組織が修復されます。
変形性膝関節症では、PRPによって軟骨の代わりとなるような組織が発生し、関節が滑らかに動くようになります。
PRP療法には治療の過程で反応痛と呼ばれる、膝の腫れや痛みが起こることがありますが、通常は数日から1週間程度で治まります。効果は治療から2~3週間後に現れ始めることが多いですが、効果が出やすい人だと、治療後1週間ほどで効果が現れ、1ヶ月後には痛みが消え、症状が改善されます。
スポーツをしている方は、治療後1ヶ月後くらいからスポーツを再開することができます。
当院で使用するPRP
PRPは、精製の方法や条件によって性質が異なり、治療の費用も精製機器の値段によって異なります。
当院では、厚生労働省より臨床使用可能な高度管理医療機器(クラスIII)として製造販売承認を受けたPRPのみを使用しています。
また、PRPの注入は、第三種再生医療(筋・腱・靭帯への注入)と、第二種再生医療(関節腔内への注入)があり、当院はその両方の承認を得ています。
KYOCERA Condensia
KYOCERA Condensiaは、市販の遠心分離機を使用して、PRPを効率的に抽出・濃縮できる調製キットです。
閉鎖系システムを採用しており、外気に触れずに血液成分を分離するため、採取した血漿成分の汚染リスクを低減できます。
また、各容器には容量メモリが付いているため、採取量を簡単に確認でき、使いやすさも向上しています。
欧米では20年以上前から普及しており、膝や肘の痛み、腱や筋肉の損傷に加え、変形性関節症の治療にも効果が期待されています。
■採取量:20ml~60ml
ジンマーバイオメット
APSシステム(次世代PRP)
APSシステムとは、次世代PRPと呼ばれる「APS」を生成する精製機器です。
APSは、PRPをさらに遠心分離し特殊加工することで、炎症を抑制するたんぱく質と軟骨を保護する成長因子を高濃度に抽出したものです。
APSは、PRPがもつ疼痛抑制効果や組織修復効果に加えて、軟骨の変性や破壊を抑える効果があります。
APSによる再生医療は、欧州の臨床実験において、中程度の変形性膝関節症の治療に対し、1回の注入で最大24ヶ月間にわたって、痛みと機能の改善効果があったと報告されています。
当院では、第二種再生医療(関節腔内への注入)として使用します。
■採血量:55ml
PRP療法の治療の流れ
1診察
診察・検査にて、医師によりPRP注射が可能・適応ありと判断された場合に、PRP療法をお受けいただけます。
診察にて医師とPRP療法の計画を立て、適切な量や時期を決定します。
その計画をもとに、PRP療法のご予約をお取りいただきます。
- 各種画像検査(レントゲン撮影、エコー検査など)
- 血液検査(血小板数、感染症の有無など)
2採血
採血を行います。
※通常の採血とほぼ同量の約20mlの血液を採血いたします。
3抽出
専用の機械を使用し、採取した血液からPRPを抽出します。
4注射
抽出されたPRPを患部に注射します。
PRP療法の回数
PRP療法における幹部への注射回数に制限などはありませんが、一般的には肉離れの治療で2,3回程度、腱炎などの治るのに時間がかかるスポーツ障害などは1~3回程度治療を受けていただくことが多いです。
変形性膝関節症や関節炎の治療では、患者様によってばらつきが大きく、治療後も痛みが再発した場合は、改めてPRP療法を受けていただくことがあります。
PRP療法の料金(税込)
PRP療法は、健康保険適用外の治療法となるため、全額自己負担となります。
PRP療法にかかる費用も導入している機材や薬剤、医療機関によって異なります。
| 治療内容 | PRP療法の種類 | 料金(税込) ※2回目以降、各種1割引き |
| 筋・腱・靱帯への注入(第三種再生医療) |
京セラ社製 Condencia |
66,000円 |
|---|---|---|
| 関節腔内への注入(第二種再生医療) |
京セラ社 Condencia |
66,000円 |
| ジンマーバイオメット社製 APSシステム (2種、関節のみ) |
330,000円 |
キャンセル料
| 治療種類 | キャンセルの時期 | 料金(税込) |
| 京セラ社製 Condencia (2種・3種、各1部位) |
採血後 |
5,500円 |
|---|---|---|
|
加工後 |
キット原価、製造作業費として33,000円 |
|
| ジンマーバイオメット社製 APSシステム (2種、関節のみ) |
採血後 |
5,500円 |
| 加工後 | キット原価、製造作業費として220,000円 |
PRP療法の除外基準
以下のようにPRP療法を実施できない場合があります。
また、患者様の健康状態などを考慮して、医師が治療の提供の可否を判断いたします。
- がんと診断されている
- 抗がん剤、生物学的製剤または免疫抑制剤を使用している
- 本治療を1ヶ月以内に受けたことがある
- 活動性の感染がある
- 血液感染症がある
- 重篤な合併症(心疾患、肺疾患、肝疾患、出血傾向、腎疾患、コントロール不良な糖尿病および高血圧症など)がある
- 薬剤過敏症の既往歴がある
- 血液検査で血小板の異常があった
幹細胞(脂肪由来幹細胞)
治療について
 幹細胞とは、自身とまったく同じ細胞に分裂する「自己複製能」と、他の様々な細胞に分化する「多分化能」を併せ持つ細胞です。幹細胞には多能性幹細胞と組織幹細胞があり、現在一般的に臨床で使用されているのは組織幹細胞となります。中でも採取のしやすさや扱いやすさから脂肪組織における間葉系幹細胞が注目されており、再生医療に用いられます。幹細胞は、損傷した組織や器官を修復するほか、減少した細胞を感知して代わりとなり、血管新生や組織修復を促す因子やサイトカインを放出する作用があります。幹細胞治療は、変形性膝関節症や脳梗塞、糖尿病、肝硬変、神経性疾患などの難病の治療、健康増進や抗加齢医療など様々な病態に効果があるといわれています。当院の幹細胞を用いた膝の再生医療は、患者様ご自身の細胞と血液を用いた治療法であるため、副作用のリスクが小さい治療方法です。
幹細胞とは、自身とまったく同じ細胞に分裂する「自己複製能」と、他の様々な細胞に分化する「多分化能」を併せ持つ細胞です。幹細胞には多能性幹細胞と組織幹細胞があり、現在一般的に臨床で使用されているのは組織幹細胞となります。中でも採取のしやすさや扱いやすさから脂肪組織における間葉系幹細胞が注目されており、再生医療に用いられます。幹細胞は、損傷した組織や器官を修復するほか、減少した細胞を感知して代わりとなり、血管新生や組織修復を促す因子やサイトカインを放出する作用があります。幹細胞治療は、変形性膝関節症や脳梗塞、糖尿病、肝硬変、神経性疾患などの難病の治療、健康増進や抗加齢医療など様々な病態に効果があるといわれています。当院の幹細胞を用いた膝の再生医療は、患者様ご自身の細胞と血液を用いた治療法であるため、副作用のリスクが小さい治療方法です。
脂肪組織の中にごく少量だけ含まれる幹細胞、「脂肪組織由来幹細胞」を培養し、投与することでその効果を得られます。
PRPと比較されることが多いですが、一般的に幹細胞治療の方が効果は高いとされています。
「幹細胞」の特徴
多分化能
構成するさまざまな細胞に変化する能力。身体の成長や組織の再生に重要な役割を果たします。
自己複製能
同じ能力を持つ細胞に分裂することができる能力があります。
ホーミング現象
幹細胞には治療必要部位に集積する性質があり、これをホーミング現象といいます。
パラクライン作用
細胞が分泌するエクソソーム、成長因子、サイトカインなどの分子が、近接する細胞や組織に直接影響し炎症の調節や繊維化の改善を促します。
免疫調節効果
自己免疫疾患や器官移植後の免疫反応を調節する効果も期待されています。
幹細胞治療の適応疾患
- 変形性関節症(肩、肘、股、膝、など)
- スポーツ外傷などによる運動器障害
- 神経変性疾患
- 脊髄、神経損傷
- 臓器障害
- 動脈硬化症
- 脱毛症
- 慢性疼痛
- ロコモティブシンドローム、フレイル
ロコモティブシンドローム、フレイルとは
フレイルとは フレイルとは、年齢を重ねることで心身の働きが低下し、外から受ける様々なストレスに対して抵抗力が弱まった状態です。健康状態と要介護状態の中間の段階ともいえます。
日本語では「虚弱」を意味する医療用語です。 似た状態として、2007年に日本整形外科学会から提唱された「ロコモティブシンドローム」が挙げられます。
ロコモティブシンドロームは、身体動作や姿勢の維持に必要となる運動器に発生した障害により移動機能が低下した状態で、近年注目が集まっています。
日本医学会連合が発行する患者様用のパンフレットでもその危険性に触れられており、ロコモを放置して重症化した場合、身体的フレイルに至ると記載されています。
また、フレイルは以下の4つがリスク要因となります。
- 集団特性・社会的要因:年齢、性別、居住環境など
- 臨床的要因:栄養関連要因、肥満や認知症など別の疾患
- 生物学的要因:ビタミン不足、慢性炎症や内分泌因子(ホルモン)異常など
- 生活習慣の乱れ:喫煙、アルコールの過剰摂取、運動不足など
当院ではフレイルに対して幹細胞治療を行っています。この治療は3番目の慢性炎症に注目した治療となっており、炎症を抑えることでフレイルの発症・悪化を防ぐ効果が期待できます。また、患者様ご自身の幹細胞を用いるため、拒絶反応や副作用のリスクが低いことも特徴です。 フレイルにお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
今後当院で対象として導入予定の疾患
- 筋肉・腱・靭帯損傷
- 慢性疼痛
- ロコモティブシンドローム、フレイル
- 脊髄損傷・難治性脊髄症
幹細胞治療の流れ
1診察
まずは医師による診察を受けていただき、幹細胞治療が可能・適応ありと判断された場合に、治療をお受けいただけます。
診察では、治療の内容と計画についてご説明いたします。
幹細胞治療をお受けいただく場合は、当院より同意説明文書を用いた説いたします。
同意していただいた場合は、同意書に署名していただきます。
2適格性の検査
血液検査による感染症の検査(B型肝炎、C型肝炎、HIV、HTLV-1など)と、がん検診(PET検査、腫瘍マーカー検査など)を行い、適格性を調べます。
適格性検査の結果に問題がなかった場合は、幹細胞を培養するための脂肪採取の日程を調整します。
検査結果は検査から5日後に確定します。結果は当院よりご連絡いたします。
3幹細胞(脂肪由来幹細胞)
1脂肪の採取
幹細胞を培養するための脂肪と血液を採取します。
脂肪の採取は、通常腹部の皮下脂肪から行い、1~3g程度採取します。局所麻酔を使用するため、痛みはありません。
また、細胞の培養に血液が必要になるため、200ml程度の採血を行います。
施術は1時間程度で終了します。施術後はそのままお帰りいただけます。施術から1週間後に抜糸を行います。
2幹細胞の培養
採取した脂肪を、細胞培養加工施設(CPC)に送り、脂肪組織から取り出した幹細胞を培養します。
幹細胞は約4~6週間で必要な数まで培養することができます。
培養した幹細胞は、投与に問題がないかを確認する試験を行ったのち、冷凍保存されます。
3幹細胞の投与
培養し冷凍保存した幹細胞を解凍し、幹細胞の生存を確認してから幹細胞を投与します。
投与は、脳梗塞や脊髄損傷の後遺症に対して行う場合、1時間程度かけて点滴します。
変形性膝関節症の場合は、関節内に注射器を用いて直接投与します。
変形性膝関節症の方のみ、投与後そのままお帰りいただけます。
4投与前後のモニタリング
幹細胞の投与後は、安全性と効果の確認のために、投与から1年後に投与前の状態と比較して、評価を行います。
幹細胞移植治療プランと料金(税込)
| 項目 | 料金(税込) | |
| カウンセリング・初診料 |
5,000円 |
|
|---|---|---|
| 血液検査 |
11,000円 |
|
| 細胞採取 |
220,000円 |
|
自家脂肪由来間葉系幹細胞
| 治療範囲 | 細胞数 | 料金(税込) |
| 片側 |
5,000万cells |
660,000円 |
|---|---|---|
|
1億cells |
880,000円 |
|
| 両側 |
1億cells(片側5,000万cells) |
1120,000円 |
| 2億cells(片側1億cells) | 1450,000円 |
細胞保管費用(1か月あたり)
| 項目 | 料金(税込) | |
| 細胞保管費用 |
11,000円 |
|
|---|---|---|
キャンセル料
| 項目 | 料金(税込) | |
| 脂肪採取前まで |
なし |
|
|---|---|---|
| 脂肪採取後、投与予定日の28日前まで |
投与費用の50% |
|
| 投与予定日の27~14日前まで |
投与費用の80% |
|
| 投与予定日の13日前~投与当日 |
投与費用の100% |
|
PRPと幹細胞の違い
膝の再生医療に関しては、「PRP(多血小板血漿)」を用いた治療法と「幹細胞」を用いた治療法の2種類があります。
PRPは自身の血小板を濃縮したものであるのに対して、幹細胞は細胞そのものです。
そのため、PRPよりも幹細胞の方が修復力は、圧倒的に高いという特徴があります。
PRPは組織の修復を促すのに対し、幹細胞はそれ自体が必要なところに加わり組織を再生していくというイメージです。
2種類の違い
| 種類 | 治療に使うもの | 向いている方 | 特徴 |
| PRP(多血小板血漿) | 自身の血小板 | 比較的軽症な方 | 幹細胞より安価 |
|---|---|---|---|
| 幹細胞(ひざの再生医療) | 自身の幹細胞 | 重症な方 ・しっかり治したい方 | 修復力が高い ・低リスク |
当院における再生医療の
特徴・メリット
PRP療法と幹細胞治療の両方の治療が可能
当院では、PRP療法と幹細胞治療のどちらにも対応しているため、患者様に合わせてご希望の治療方法を選択していただけます。
また、PRPと幹細胞を併用した治療を行うことも可能です。
いつでも再生医療を中止して、保険医療に切り替えが可能
当院は保険医療機関であるため、再生医療に効果が感じられなかったり、費用面などの理由で、再生医療を中止したい場合は、健康保険適用外の再生医療から、いつでも健康保険適用となる診療に切り替えることが可能です。
また、人工関節などの手術を希望される場合は、提携先の医療機関を紹介いたします。
培養脂肪数が多い
当院では、幹細胞を5000万個以上になるまで培養し、治療に用いているため、高い治療効果が得られます(通常は3000万個程度)。1億個の幹細胞を用いた治療も可能です。
脂肪採取は1回だけでよい
採取した脂肪は、指定培養会社にて凍結保管されているため、追加で培養が必要な場合も、再び脂肪を採取する必要はありません。培養は、凍結保管されている脂肪細胞と血液で行うことができるため、追加の際は採血のみで幹細胞治療を行うことができます。
院内にリハビリテーション施設がある
 当院には、リハビリテーション施設が併設されているため、再生医療によって修復した膝関節のリハビリテーションをスムーズに行っていただくことができます。
当院には、リハビリテーション施設が併設されているため、再生医療によって修復した膝関節のリハビリテーションをスムーズに行っていただくことができます。
リハビリテーションは再生医療を用いて治療を行っていくうえで重要です。
再生医療によって修復した膝関節は、リハビリテーションによって膝関節周辺の筋肉を鍛えることで、関節に強い負荷がかかることを防ぐことができます。
よくある質問
再生医療について
再生医療は、健康保険適用で受けることはできますか?
現在日本においては、再生医療は健康保険適用外の自費診療となります。
患者様に全額費用負担していただく必要があります。
再生医療の効果には個人差がありますか?
どのような治療でも、患者様によって効果に差があります。
同じ疾患や同じ程度の状態でも、高い効果が出ることもあれば、人によっては効果を感じられない場合もあります。
再生医療後のリハビリテーションはどのようになりますか?
治療後は、炎症を抑える必要があるため、はじめは筋肉強化を目的とするような負荷をかけるリハビリテーションは行わずに、筋肉の柔軟性をあげていくようなストレッチから行います。
最初のリハビリテーションは椅子に座って行うストレッチをお勧めしています。
炎症が落ち着いてきてからは、ストレッチに加えて筋肉強化リハビリテーションを行い、痛みを予防していきます。
再生医療は、医療費控除の対象となりますか?
治療を目的としているため医療費控除の対象となることがあります。
医療費控除を受けるためには確定申告を行っていただく必要があります。
※医療費控除を受ける場合は、治療費の領収書を確定申告の際に提出する必要があるため、大切に保管ください。
PRP療法について
PRP療法に副作用はありますか?
副作用はほぼありません。腱や筋肉など患部に直接、注射でPRPを投与するため、治療中や治療後に痛みが出ることはあります。
しかし、関節腔内にPRPを注射する場合は、痛みが起こることは少ないです。
また、注射後から約2週間は組織を修復する過程で起こる炎症により痛みが起こる場合があります。
PRP療法は効果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?
PRP療法は、直接組織を修復するのではなく、組織の修復力を促進するものであるため、即効性はなく、人によって効果が出るまでの期間は様々です。
通常は、1週間から6ヶ月の間に組織が修復され、その過程で痛みが軽減し、効果を実感することができます。
PRP療法のメリット・デメリットはどのようなものがありますか?
PRP療法のメリットは、患者様ご自身の血液から精製したPRPを使用して治療を行うため、副作用が少ないことが挙げられます。
PRP療法のデメリットは、健康保険適用外の自費診療となるため、費用の負担が大きいことが挙げられます。
治療後の生活で注意することはありますか?
PRP療法を受けた当日は、患部のマッサージや運動、飲酒は控えるようにしてください。
また、関節腔内へ注射をした場合は、治療当日の入浴も避けるようにしてください。
治療の翌日以降は、通常通りに生活していただいて構いません。
痛みが治まれば、運動も行っていただけます。
PRP療法に年齢制限はありますか?
PRP療法に年齢制限はありません。
治療による体への負担も少ないため、幅広い年齢層の方にお受けいただいています。
幹細胞(脂肪由来幹細胞)治療について
どんな効果がありますか?
抗炎症作用と創治癒能力により疼痛の緩和、症状の改善を期待できます。
年齢制限はありますか?
幹細胞治療は基本的には18歳以上の方を対象とさせていただいております。
幹細胞の培養のための脂肪は、体のどこから採取しますか?傷痕は残りますか?
脂肪組織のある部位でしたらどこからでも採取可能ですが、 当院では、腹部や臀部など合併症が少なく目立ちにくい場所からの採取をお勧めしています。
脂肪はどのくらいの量を採取しますか?
皮膚を2~3cm程度切開し、小指の爪ほどの量の脂肪組織を採取します。
採取にかかる時間は10分程度です。
脂肪採取から幹細胞投与までの期間はどれくらいですか?
培養には6週間程度かかります。
脂肪採取後に気を付けることはありますか?
当日は入浴、飲酒、激しい運動は避けてください。
投与する幹細胞の数はどのくらいですか?
特に決まりはありませんが、ひざの再生医療ですと、片方の膝で5000万個くらいからが、効果は高くなるとされています。
投与は何回くらい必要ですか?投与の度に毎回脂肪を摂取する必要はありますか?
効果には個人差がありますが、2~3回の実施で効果を実感することが多いです。
脂肪は、最初に採取してから凍結保管しているため、移植の度に脂肪を摂取する必要はありません。
ただし、細胞保管のために費用や、細胞の培養には血液が必要になるため、投与の度に採血を行っていただく必要があります。
幹細胞の投与は、両膝を同時に行うことはできますか?
可能です。
また、痛みの程度に応じて、左右の膝で投与する幹細胞の数を変えることも可能です。
幹細胞の投与後に、痛みはありますか?
痛みに個人差はありますが、投与後に反応痛が起こることがります。
反応痛は1週間程度で軽減することが多いです。
また、一般的に反応痛が強いほど治療効果が現れやすいとされています。