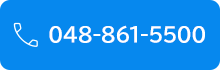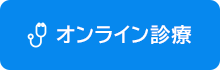当院のリハビリテーション
について

リハビリテーションでは、機能が低下した運動器の改善を図り、立ち上がる、歩く、階段を昇るなどの日常生活の動作やスポーツ活動の動作を維持、もしくは再び獲得するための訓練や強化を行います。
リハビリテーションは、日常的に起こる肩こりや骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、関節リウマチなどの疾患、骨折などの外傷によって運動器が障害された状態のときに行われます。
また、手術後などには、運動器の失われた機能をできるだけ早く取り戻す目的で行われます。
その他にも、健康寿命の増進や介護予防などを目的として、足腰を強くすることもリハビリテーションの一部です。
「健康寿命を延ばす」
ことに注力
リハビリテーションでは、体を動かすことで筋力や筋肉の柔軟性、バランス能力を高める「運動療法」と、温熱、超音波、低周波、電気などの物理的刺激で症状を緩和する「物理療法」を組み合わせて、症状を改善していきます。
また、リハビリテーションは、患部の負担を軽減するだけでなく、再発防止にもつながります。
当院ではリハビリによって「健康寿命を延ばす」ことにも注力しております。
治療は、患者様の運動器の症状に応じて、最適なリハビリメニューを組み、施術や指導を行っていきます。
日常動作やセルフケアについてもわかりやすくお伝えします。
痛みの時期に応じた
リハビリテーション
リハビリテーションは、症状や痛みの状態、回復段階などによってリハビリテーションを行う目的や内容が異なります。
急性期
発症から3週間程度までの時期(急性期)は、症状や痛みを抑える目的で薬物療法を積極的に行い、できるだけ患部を動かさないようにし、必要に応じて固定します。
温熱、超音波、低周波、電気などの物理療法も症状や痛みを抑える上では有効です。
状態によっては、筋力の低下や関節が固まってしまうことを防止するために運動療法を行うこともあります。
回復期
症状や痛みが落ち着いてくる回復期には、筋力や筋肉の柔軟性を向上させる目的で運動療法を行い、患部の負担を軽減します。
また、運動療法の効果を高める目的で物理療法も行われます。
正しい姿勢や日常生活に関する指導なども回復期に行われます。
リハビリテーションが
必要な症状
リハビリテーションが必要な症状は、骨折などの外傷や、手術後のケアだけでなく、日常生活に支障をきたしている肩こりから交通事故によるむち打ち症など多岐にわたります。
また、骨粗鬆症や関節リウマチなどの疾患も適切なリハビリテーションを行うことで改善が期待できます。
- 関節の痛みや変形、動かしにくいなどの可動域制限
- 日常生活に支障を生る首や肩のこりや痛み、腰痛など
- 交通事故によるむち打ち症(外傷性頚部症候群・頚椎捻挫)など
- 歩くペースが遅い、歩くのに不安がある、休み休みの歩行になる
- 日常的な動作(食事・着替え・トイレなど)で思うように動けないことがある
- 麻痺や筋力低下、こわばり、しびれなどで動作しにくい
- 手術後に痛みなどの症状が続く
- スポーツによる慢性的な痛みや動かしにくさ(スポーツ障害)
当院のリハビリテーション
内容
運動療法
運動療法とは、体を動かすことで筋力や筋肉の柔軟性、バランス能力を高める治療です。
施術によって痛みを緩和したり、狭くなってしまった関節の可動域を改善することで、力をうまく入れることができない、転びやすいなどの症状を改善します。
筋力増強訓練
(筋力トレーニング)
筋力トレーニングのことです。理学療法士の補助の下でスクワットやかかと上げ、膝伸ばしなどの動作を行うことで、適切に筋肉を強化し、患部への負担を軽減します。
トレーニングのメニューは、患者様の症状や痛みの状態に合わせて負担なくできるように組みます。
歩行訓練
歩行力を改善する訓練です。
歩行訓練では、平行棒を用いた前後左右の移動訓練、歩行器・松葉杖、ステッキなどを用いた訓練、段差や階段を用いた歩行訓練など患者様の状態に応じて適切な訓練を行います。
関節可動域訓練
術後の影響や痛みのために狭くなってしまった関節の可動域を広げるための訓練です。
この訓練では、理学療法士の補助の元、痛みを感じる位置まで対象箇所を動かしていきます。
バランス能力の訓練
落ちてしまったバランス能力を向上させる訓練です。
バランスが良い状態というのは、静止する動作と動く動作のどちらも安定していて、外力が加わっても動作が保たれる状態のことをいいます。
高齢になると、静的バランスと動的バランスのどちらも機能が低下するため、転倒しやすくなります。
バランス能力は様々な要因が関係します。そのため、バランスを崩しやすい状況や、バランスを崩しやすい方向、バランスを崩す頻度などをもとに原因を追究し、転倒防止の戦略を立てていきます。
徒手療法
徒手療法とは、理学療法士が手を用いて行う治療法の総称です。筋肉や関節の機能改善を目的に行います。
マッサージ、ストレッチング、関節モビライゼーション、軟部組織モビライゼーション、筋膜リリースなどが含まれます。
また、装具の調整なども含まれます。
関節モビライゼーション
関節の動きを改善し、痛みを軽減する徒手療法で、関節の可動域が狭まり、動作に支障がある場合に行います。
関節を様々な幅で繰り返し動かすことで可動域をゆっくりと広げていきます。
軟部組織モビライゼーション
筋や筋膜、腱などの軟部組織をマッサージすることで、痛みを軽減したり、運動機能を改善する治療法です。
専用のバーやへら状の器具を用いてマッサージを行うこともあります。
筋膜リリース
ストレッチやマッサージなどを用いて、筋膜(筋肉を覆っている膜)癒着や萎縮をほぐす施術です。筋膜は筋肉を使わなかったり、反対に使いすぎることで硬くなり、筋肉と癒着し、不調を起こします。
また、ハイドロリリースという超音波画像によって筋膜周辺を確認しながら、筋膜へ薬剤を注射することで筋膜の癒着を剥がす方法もあります。
物理療法
物理療法は温熱、超音波、低周波、電気などの物理的な刺激によって血行や運動機能の改善を促す治療です。
運動療法と適切に組み合わせることで相乗効果を得られます。
超音波療法(温熱・音圧)
20kHz以上の人間の耳では聞くことができない高い周波数の「超音波」を患部に照射することで、人体深部の組織を加温し、血行を改善したり、炎症を抑える治療法です。
また、超音波を受けると生体内にある数μm程度の小さな気泡が圧縮と膨張を繰り返し、細胞膜が刺激され、細胞が活性化します。
超音波骨折治療器
LIPUS(低出力パルス超音波)を骨折部位に照射することで、LIPUSの音圧効果によって、骨癒合期間(骨がくっつき修復されるまでの期間)が短縮されます。
現在は難治性骨折などの治療の場合にのみ健康保険適用となります。
治療は、患部に超音波骨折治療器を当てるだけで、痛みはなく、所要時間は20分程度です。
装具療法
コルセットやサポーター、テーピング、インソール(中敷き)などの装具を装着することで、患部の痛みや変形などを軽減したり、患部にかかる負担を軽減する治療法です。
装具にはプラスチックや金属プレートから構成される硬性装具と、布地などの柔らかい素材で構成される軟性装具があります。